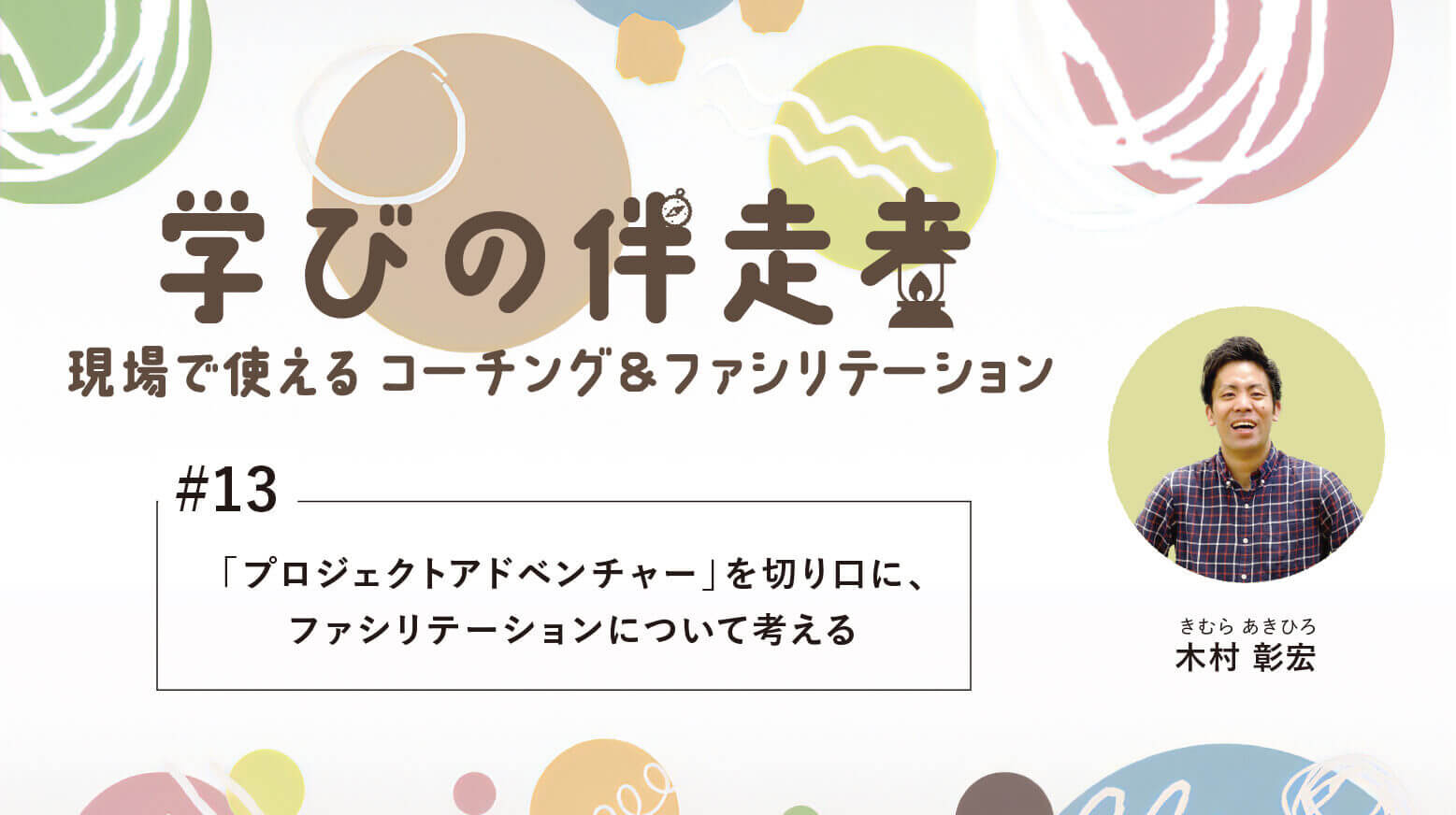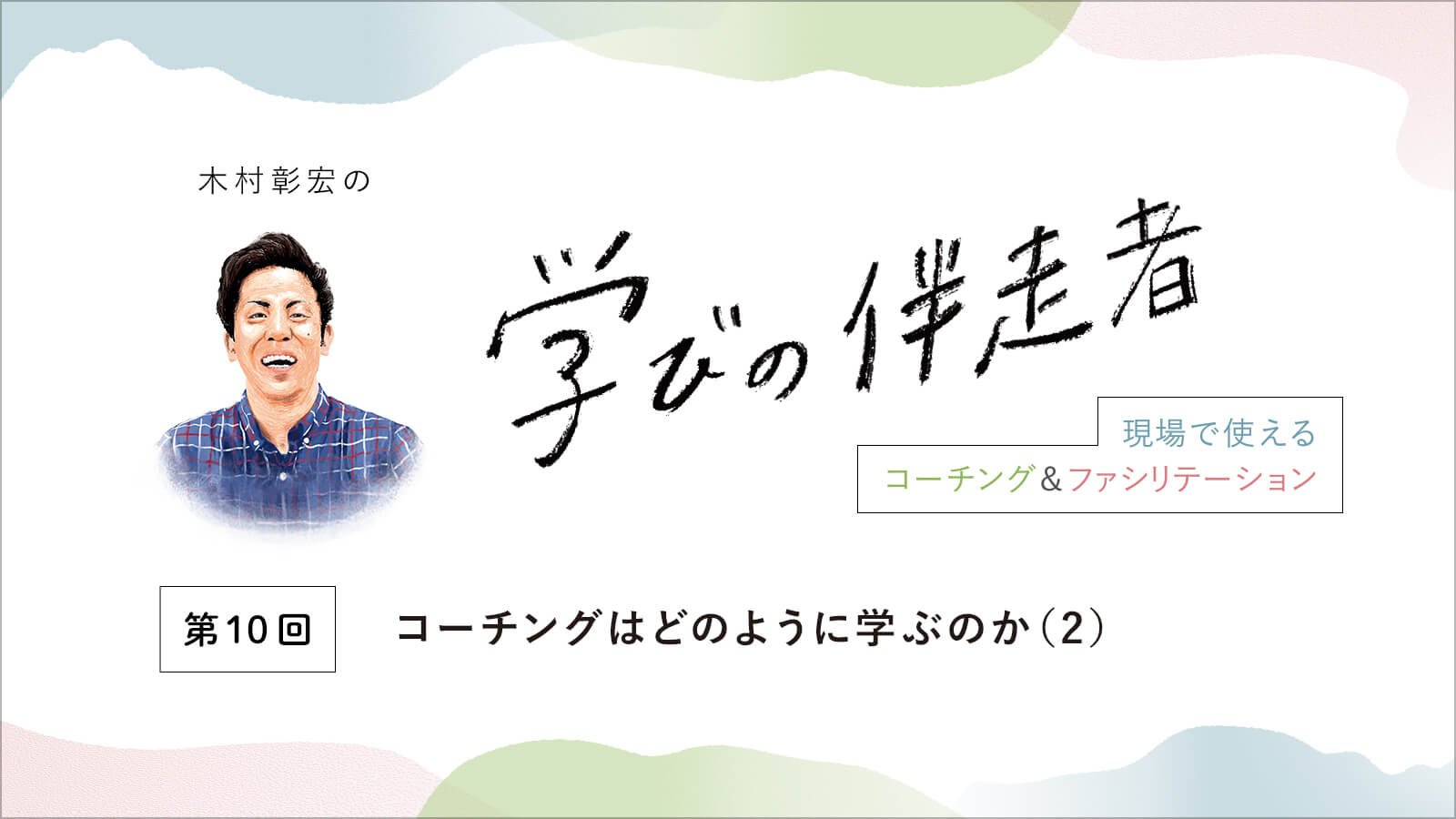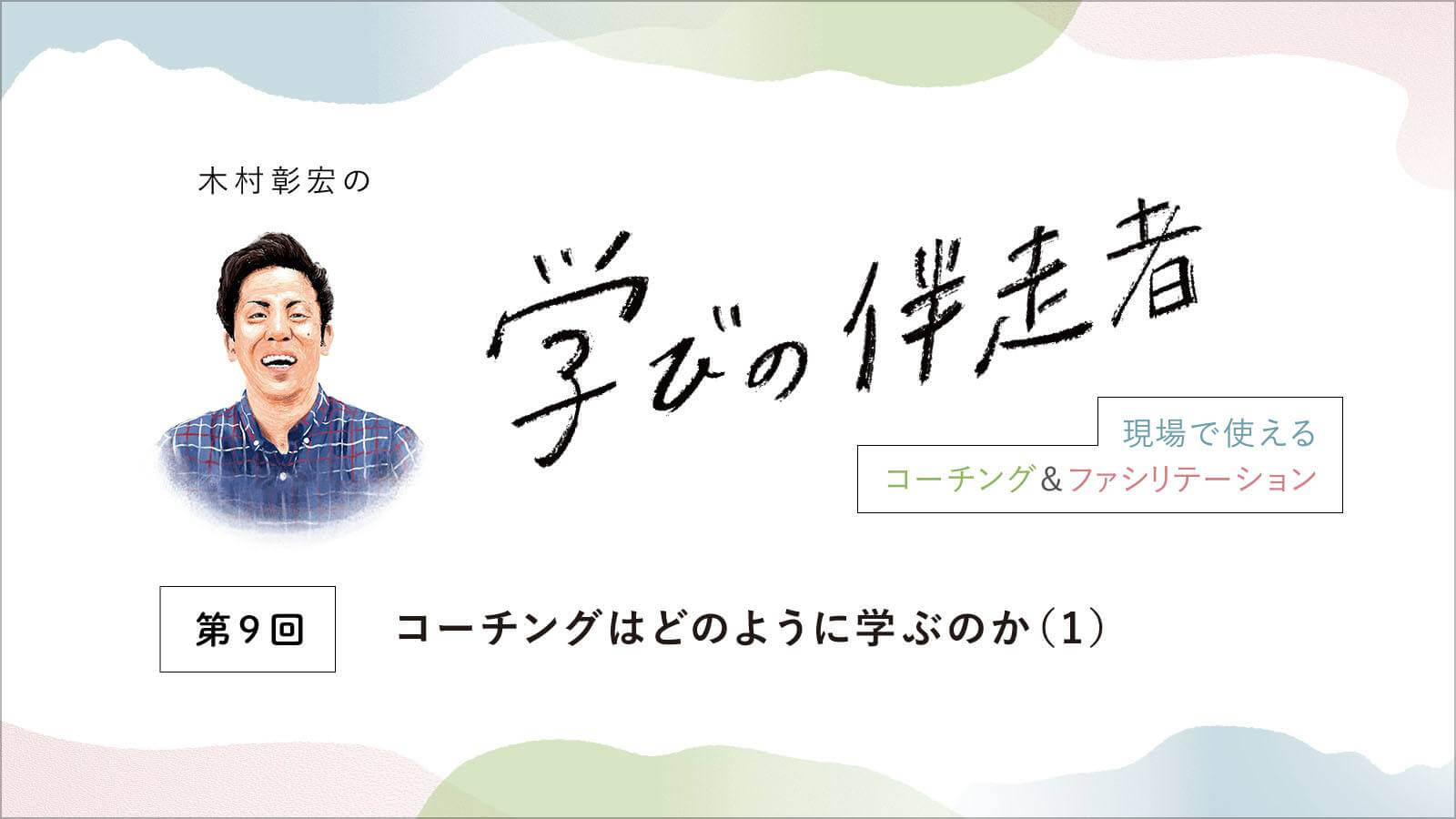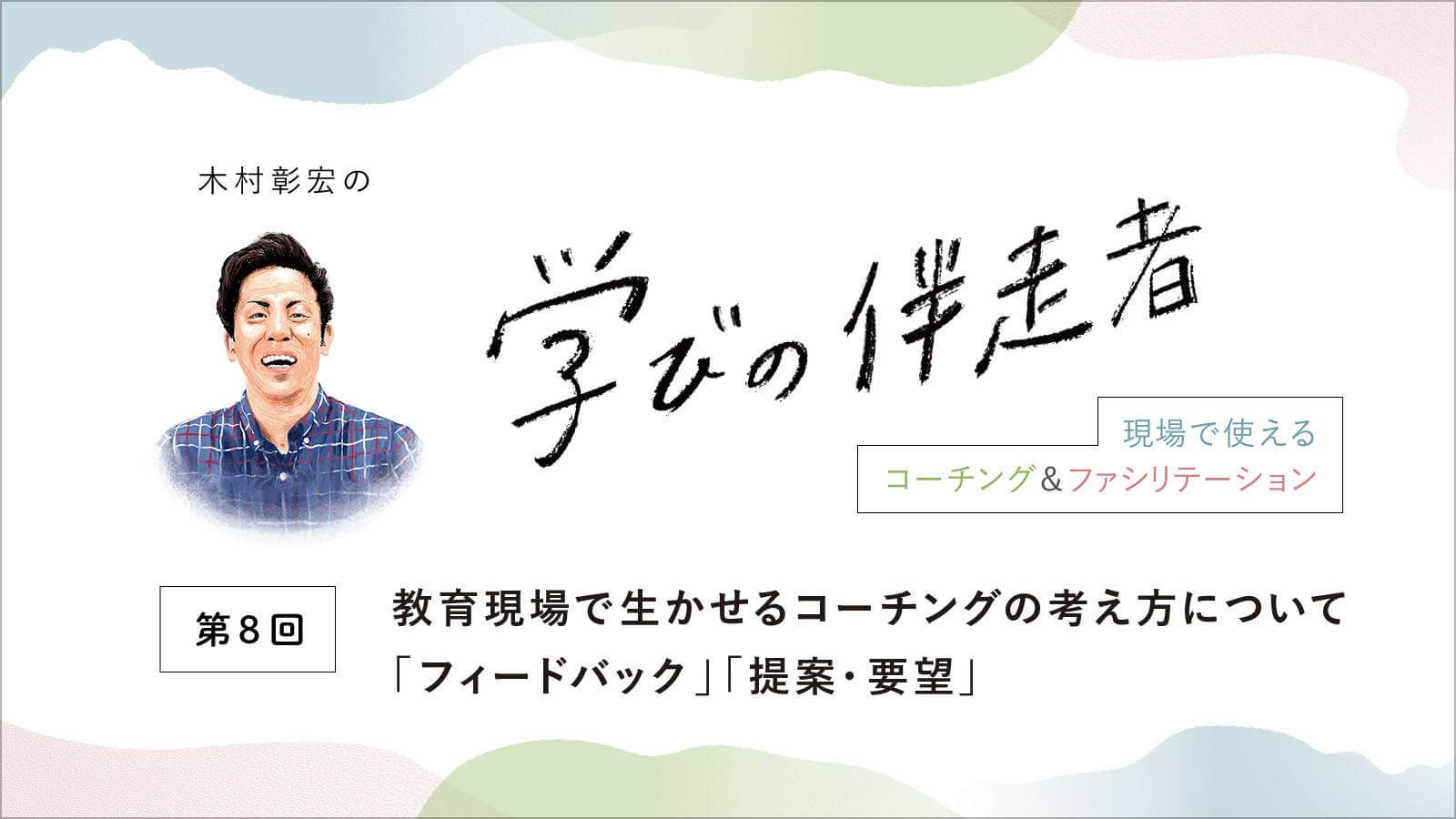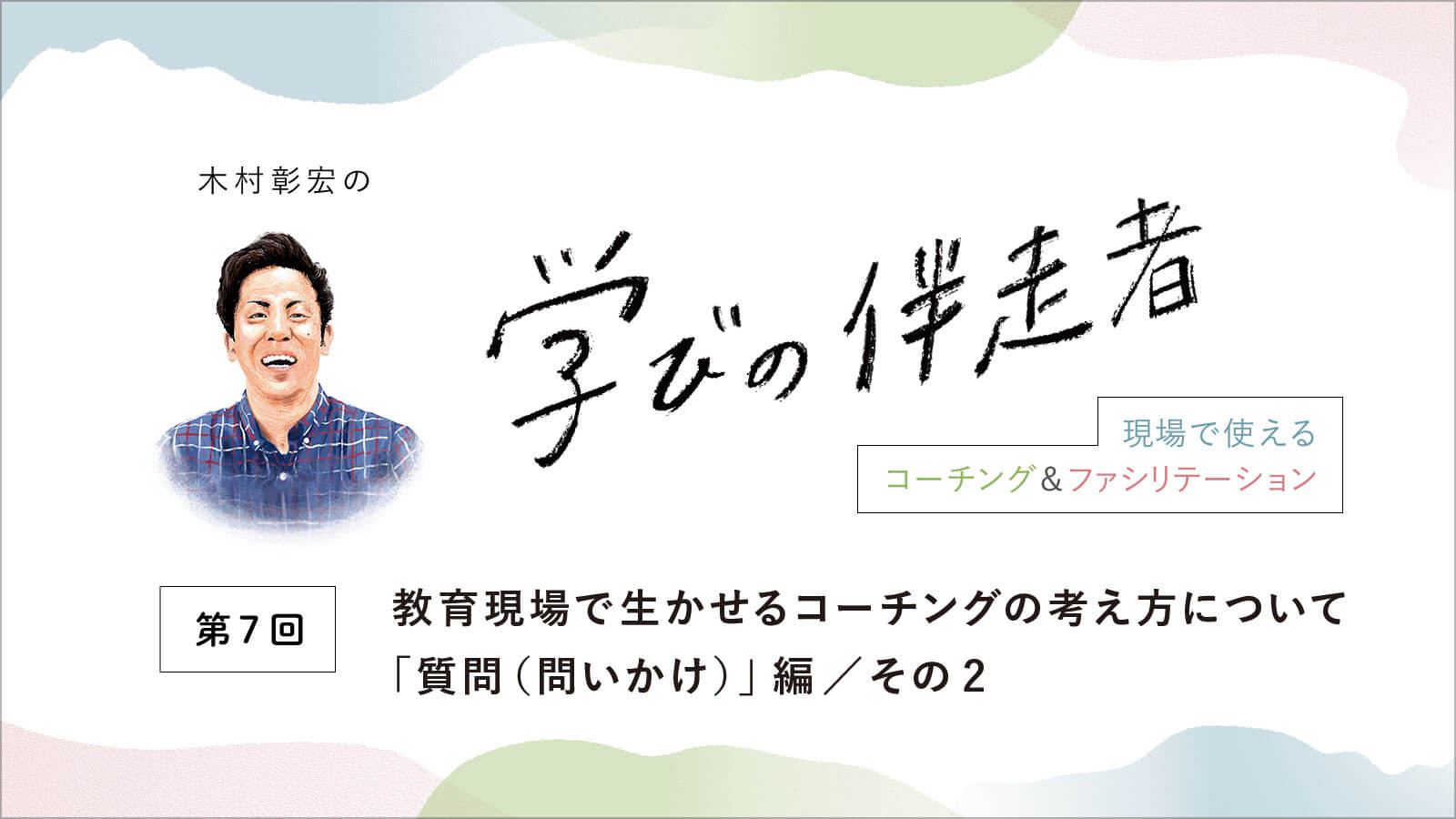【第14回】支援者の「あり方」が場の空気をつくる ── 技法以前の“being”に目を向ける
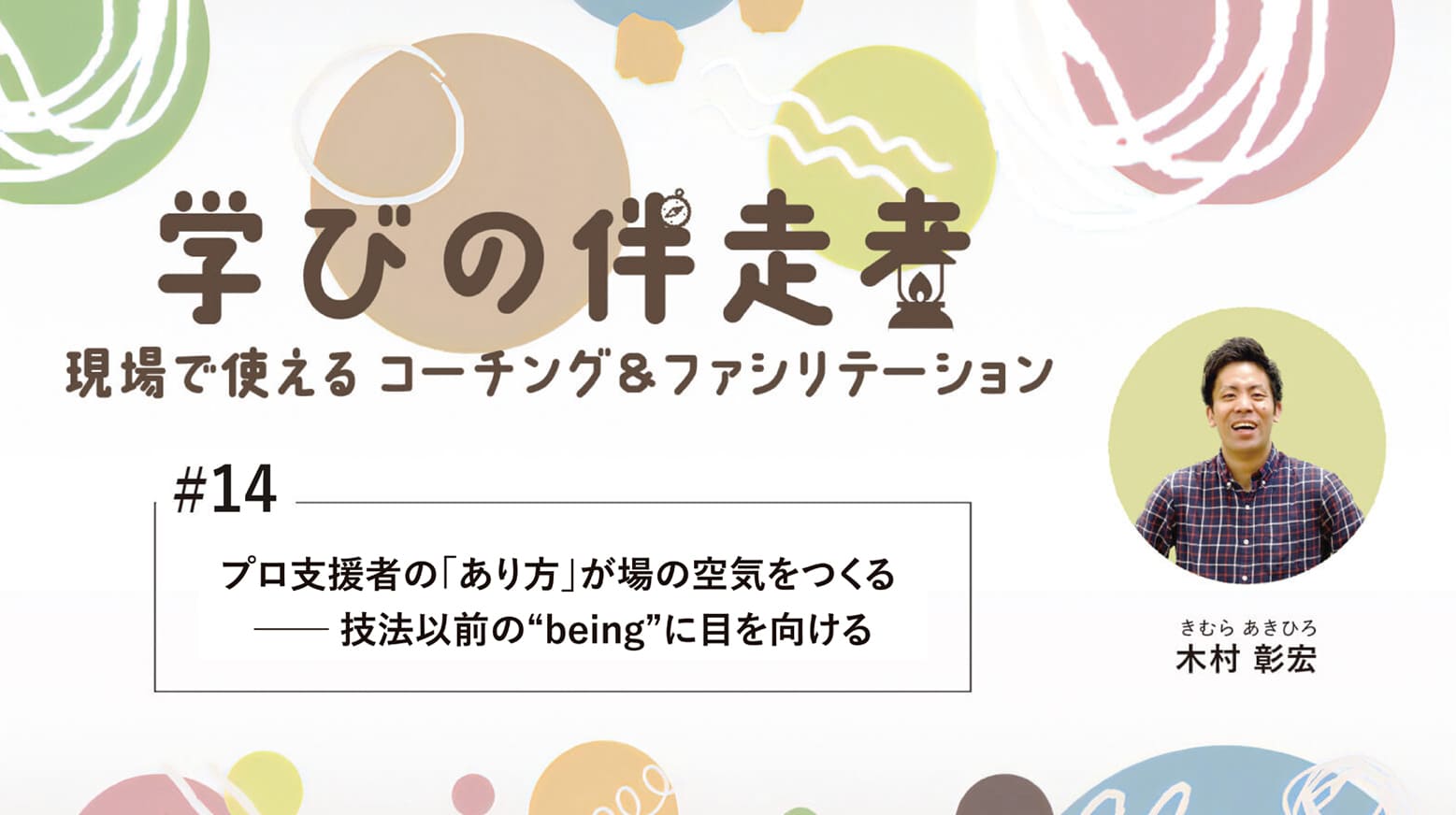
なぜ今、教育の世界で「コーチング」や「ファシリテーション」が注目されているのか?
伴走者として、学び手に関わる方々が、学び手の主体的・対話的な学びを加速させるために有効なコーチング(的な関わり)や、ファシリテーションスキルを紹介する連載です。

復興支援NPO職員、小学校の教師というキャリアの後、株式会社LITALICOに入社してLITALICOジュニア事業部にて子どもたちの発達支援に関わる。その後、人材開発部にて福祉・教育に興味関心ある学生や社会人のキャリア支援に従事。2020年4月から、コーチングを通じて起業家や経営者をサポートする株式会社コーチェットに参加し、トレーナー兼コーチとして活動。2021年4月からは、軽井沢風越学園に参画し、立ち上げ期の学校に関わる。2024年4月から「人と組織のコンサルティングファーム」株式会社MIMIGURIへジョイン。その他、複業として、プロコーチとしての業務、研修・WS設計、ファシリテーション業務、キャリア教育、教員の伴走支援などさまざまな活動を行っている。
この連載では、支援者・伴走者として学び手に関わる方々が、学び手の主体的・対話的な学びを加速させるための手段として活用できる、コーチング的な関わりやファシリテーションに関連する知識を紹介します。
本連載では、コーチングやファシリテーションの定義や方法論に固執するのではなく、紹介させていただくポイントを参照、実践いただきながら、学びの伴走者として皆さまご自身にとってのコーチング的な関わりやファシリーテーションの可能性を模索していただければうれしく思います。
第14回目となる今回は、コーチングやファシリテーションのスキルや構造を一旦離れ、支援者として「どうそこにいるか」という「存在のあり方=being」に焦点を当てたいと思います。
皆さんは、子どもと一対一で関わる時間で、傾聴や承認、問いかけといったコーチング的な関わりを意識しているにも関わらず、相手からどこか他人行儀な返事しか返ってこず、「あれ、心が通っていないな」と寂しさを感じた経験はないでしょうか。あるいは、集団をファシリテートしていて、「どうも場の空気がぎこちない…」と戸惑ったことは…?

こうした場面を掘り下げてみると、多くの場合、技術的な問題ではなく、もっと根本的な、支援者自身の「あり方」が深く関わっていることに気づかされます。
コーチングの源流であり、世界で初めて国際コーチング連盟(ICF)認定プログラムを提供したCTI(Co-Active Training Institute)は、コーチングを「Doing(何をするか)」と「Being(どうあるか)」の統合であると捉えています。これは、支援者が「何をしたか」という行動以上に、「どんな存在であったか」が、相手の変容に決定的な影響を与えるという考え方です。
CTI JAPAN代表の平田淳二さんは、Co-Active®コーチングについて次のように語っています。「コーチ自身が、その人らしくクライアントに関わることで、それがクライアントに影響を与えるのです。」つまり、私たちの内なる状態が、言葉以上に雄弁に相手に伝わってしまうのです。
では、具体的に支援者の「あり方」は、どのように場や相手に影響を与えるのでしょうか。
ケース1:1対1の関わりで、子どもの本音が見えないとき
例えば、子どもに「何があったの?」と問いかけながら、心の中では「きっとこういうことだろう」と決めつけていたり、「自由に発言していいよ」と言いながら、無意識に“正解”を探すような目で子どもを見ていたりする。あるいは「失敗を恐れずに」と励ましつつ、「これくらいはできるはず…」という期待やプレッシャーを滲ませてしまう…。
正直、私自身にもそんな経験があります。そして、そんな場面を思い返すと、子どもたちが心からの本音を話してくれたり、伸び伸びとチャレンジしたりする姿は、残念ながら稀でした。
大人がどんな言葉をかけるか(Doing)以上に、どんなエネルギーで、どんな心持ちでその場にいるか(Being)が、子どもたちの心の扉を開く一つの鍵となるのです。
ケース2:ファシリテーションで、場がシーンと静まり返るとき
集団に対しても同様です。「みんなはどう思う?」と問いかけたのに、誰も手を挙げず、沈黙が流れる…。これも、問いの内容そのものより、「どうせ先生の中に答えがあるんでしょ?」「この人は本当に私たちの意見を聞く気があるのかな?」といった、ファシリテーターの隠れた姿勢や雰囲気が、子どもたちに敏感に伝わってしまっている結果かもしれません。
「正解」を提示する教師としての問いと、「共に問いを探究する仲間」としてのファシリテーターの問い。そのあり方の違いが、受け手の姿勢や対話の深まりを大きく左右するのです。
また、チームで対話するワークショップが形式上はうまくいっていても、「どうも対話が表面的で、本音が出ていないな」と感じることはないでしょうか。
その背後には、場を進行する自分自身のBeing、例えば「成果を出さなければ」という焦りや、「参加者を失敗させたくない」という過度な配慮が、無意識のうちに場の自由な空気を抑圧している可能性も潜んでいます。

ここまで「あり方」の重要性をお伝えしてきましたが、だからといって「正しいあり方」や「理想の支援者像」を追い求め、自分を型にはめようとすると、かえって苦しくなってしまいます。
大切なのは、完璧な存在を目指すことではありません。どんな自分であっても、まずは「今の自分のあり方」を自覚し、そこに意識的であること。緊張しているなら、その緊張を。不安があるなら、その不安を否定せずに受け止める。
その「ありのままの自分」と真摯に向き合いながら相手に関わっていくことが、結果として子どもたちやクライアントとの揺るぎない信頼の土台を築いていくのです。
支援者・伴走者としての技術(Doing)は、もちろん極めて重要です。しかし、その技術を真に生かし、相手の心に届ける土台となるのが、私たちの「あり方(Being)」に他なりません。どんなに優れた問いを投げかける技術を持っていても、「その問いを、誰が、どんな心持ちで投げているのか」が、相手との関係性を形作り、学びの深さを決定づけるのです。
最後に、ご自身の「あり方(Being)」を意識し、見つめ直すための問いをいくつかご紹介します。ぜひ、日々の実践の中で、ふと立ち止まり、自問してみてください。
「今、自分はどんな空気をまとってここにいるだろう?」
「この問いは、誰のために、どんな意図で投げようとしているのだろう?」
「今、自分は相手を、あるいはこの場を“支配”しようとしていないだろうか?」
「この場の中で、私はどれくらい自分を信じ、そして相手を信じられているだろうか?」
これらの問いに即答できる必要はありません。ただ、問い続けること自体が、あなた自身の「あり方」への感度を高めてくれるはずです。
今回の内容は、いかがだったでしょうか。本記事の内容が、変化が激しく未来が見通しにくい今の時代に、伴走者として学び手に関わっていらっしゃる皆さまにとって、学び手のより良い成長・発達・変容につながる一助となっていれば幸いです。
連載内容について何かご質問等ございましたら、いつでもX(旧Twitter)のアカウント(@1130kimura)や Instagramのアカウント(@akihiro113o)に DMにてご連絡くださいませ。
参考資料:
『コーチング・バイブル』(CTI著)『新版 コーチングの基本』(コーチ・エィ)
「コーチングの源流として『Being』と『Doing』からなる『Co-Active®コーチング』を広めたい」株式会社Smart相談室 note