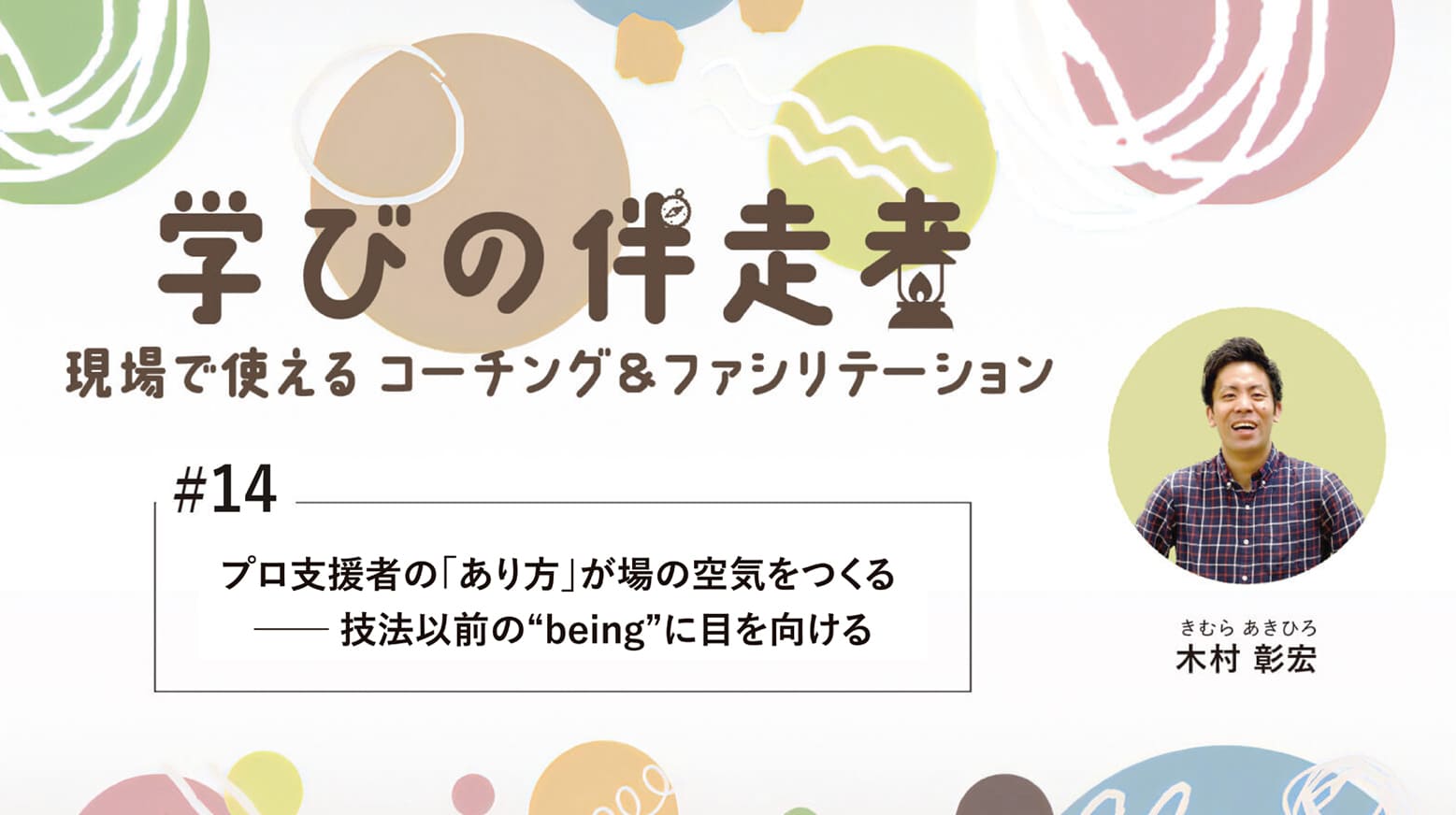“見えない違い”に目を向けることが、DEIの出発点。学校は、異文化感受性を安心して育む練習ができる場所
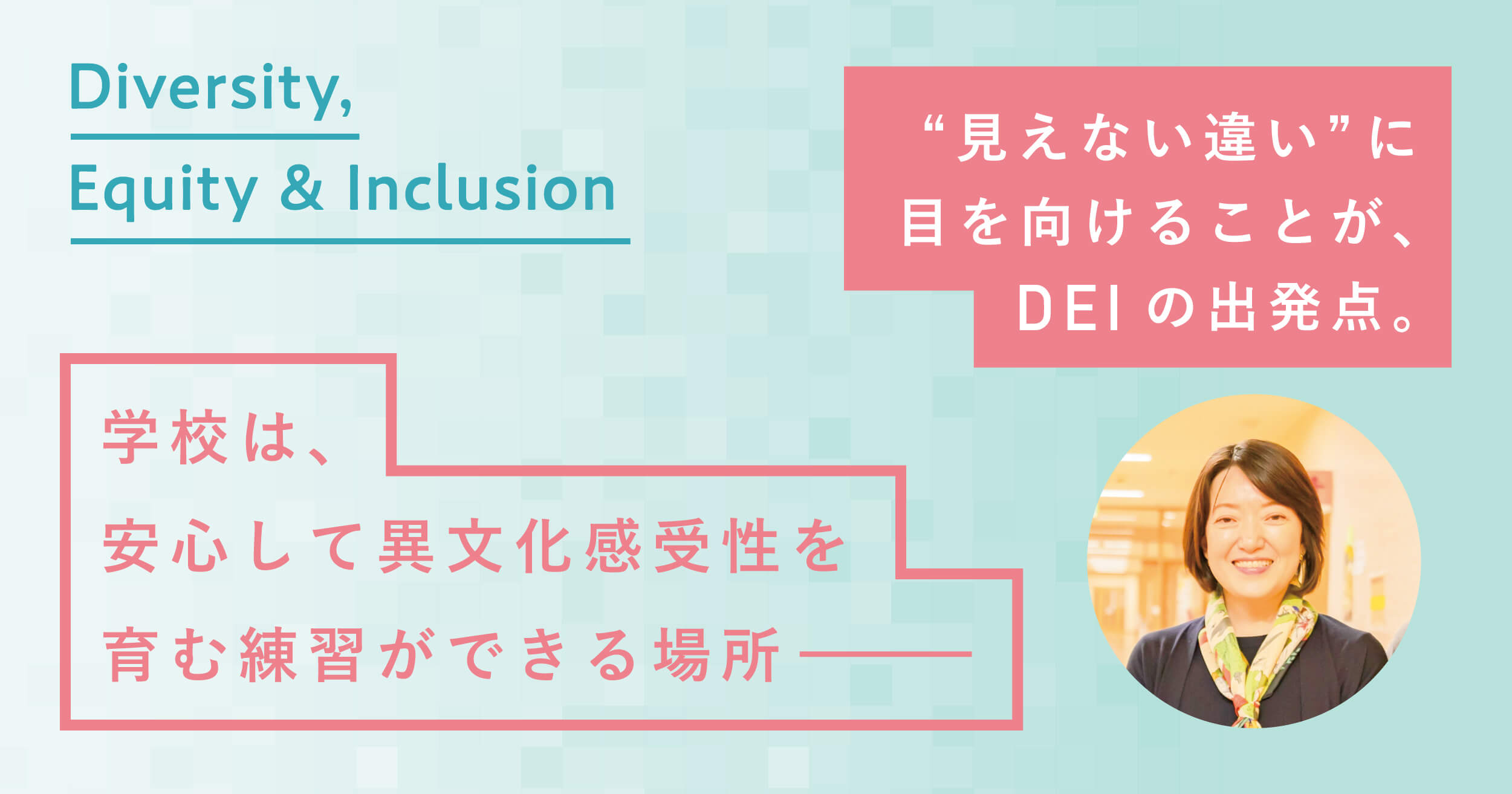
教育分野においても「DEI(多様性・公正・包摂)」という言葉を耳にする機会が増える一方で、学校現場ではどう受け止め、どう実践すればよいのか迷う声も少なくない。“違い”を「困りごと」ではなく「可能性」として捉えるためには、どんな意識が必要なのか。
異文化に対する理解や感受性を高める「異文化感受性発達」の研究と実践に長年取り組んできた、立命館大学グローバル教養学部教授の堀江未来さんは、「相手の“見えない部分”にこそ目を向ける意識が大切だ」と語る。
現在、立命館大学先進研究アカデミー「RARA」のアソシエイトフェロー(研究者)として「DEI教育」について研究する堀江さんに、じっくり話を聞いた。

名古屋大学大学院教育学研究科博士前期課程修了、ミネソタ大学(アメリカ)博士課程修了、Ph.D.(教育政策行政学)取得。学部時代の中国留学を契機に、異文化体験を通した成長メカニズムの探究を始める。学位取得後、南山大学、名古屋大学を経て2009年立命館大学国際教育推進機構に着任。2017年から7年間附属校校長を兼任し、多様な児童生徒の成長の姿に接しながら、初等中等教育におけるDEI推進に努めた。BRIDGE Institute代表。
相手の見えない部分にこそ目を向ける
ーー堀江さんは現在、立命館大学の先進研究アカデミーRARAで、「DEI教育」の研究をされているそうですね。具体的に、どのようなテーマに取り組んでいるのでしょうか?
私が取り組んでいるのは、DEI教育の実践と理論の両面をつなぐ研究です。
この研究を進めるにあたって、一旦「DEI教育」を、「社会を構成する人々の多様性を認識し、他者との対話や協働を通じて、あらゆる立場にある人の人権が守られるような、公正な社会の実現を目指す教育」とおきました。
研究の出発点は、立命館学園の小・中・高・大学での教育実践の経験です。DEIという名前を使っていなくても、趣旨を同じくするような教育実践はすでにたくさん取り組まれていますので、そういった既存の取り組みを検証しながら、DEIの推進に必要な知識やスキル、そして姿勢を育てる教育モデルを開発したいと思っています。
また、いずれは国内外でも活用できるような形へと発展させていきたいと考えています。最終的には、DEI教育の研究や実践が継続的に広がっていくための拠点づくりを目指しています。
ーー堀江さんがこのテーマに関心を持たれたきっかけはなんだったのですか?
私自身、大学入学と同時にたくさんの留学生と出会う機会があり、そこが私にとって初めての異文化との出会いでした。当時はバブル期。物価の高い日本に、ナイジェリアや中国、ミャンマーなど多様な国の学生が、母国の未来を思い、強い覚悟と情熱を持って学びに来ていました。必死に学ぼうとしている彼らの姿にとても圧倒され、心を揺さぶられたんです。
その流れで、私も中国・南京大学に1年間交換留学することになり、現地での生活を通して「目に見えることが全てではない」という異文化の奥深さに触れることになりました。
同時に、日本にいた頃は抑えていた自分の素の部分、例えば率直なもの言いや、自分の意思をはっきり示す姿勢を、現地では自然に出すことができたんです。「世界には、自分が自分らしくいていい場所が必ずあるんだ」と感じた経験は、私にとって大きな救いでした。そんな体験をした後に帰国すると、今度は逆に日本に馴染めなくなってしまったのですが…。

異文化に過適応した後、日本で強い不適応を経験した私を見て「おもしろい経験してるね」と声を掛けてくれたのが、異文化コミュニケーション論を専門にされていた先生でした。ここが、私の研究者としての出発点です。
文化の狭間に立った経験がある人は、どちらの文化にも寄り添える視点を持てるようになる。だからこそ見えるものがあり、果たせる役割がある。私自身、そうした経験に教育的意義を感じて、大学教員として大学生を対象に異文化間教育の実践を積み重ねてきました。
2017年から2024年までの7年間は、附属校の校長という立場から、より幅広い年代の子どもたちとも関わるようになり、異文化間教育の理論的枠組みをDEI教育というより広い文脈に照らし合わせて展開したいと考えるようになりました。

ーー校長という立場で学校現場に身を置いていた頃は、どのような形でDEIのメッセージを伝えていましたか?
私が校長として子どもたちに伝えてきたメッセージの根幹には、長年研究してきた「異文化感受性発達」やそれに関連する多様な論理的枠組みがあります。
これは、自分と他者を相対化し、「どちらが優れているか」ではなく、「違いがある」「共通点もある」といった認識を出発点として、自分にはまだ知らないことがあるという学びの姿勢を持ち続けることで、お互いのウェルビーイングを高めていこうとする考え方です。私はこの価値観を、子どもたちにも伝わるように、言葉や形を工夫しながら発信してきました。
異文化感受性発達理論の柱の1つは、「相手の“見えない部分”にこそ感受性を向けること」。自分が知らないことが相手にはたくさんある。そのことを学んで、自分の選択肢にも取り入れていく。そうすることで、自分自身の幅も広がっていきます。
この考え方は、まさにDEIの考え方と直結しているんです。
「自分には見えていないことがある」という意識
ーー堀江さんは、そもそもDEIをどのように捉えていらっしゃるかお聞きしたいです。
DEIの「D(Diversity/多様性)」について言えば、人は多様であるということであって、それ以上でもそれ以下でもありません。人はそもそも一人ずつ違っています。ただし、その違いを表面的なレベルだけでなく、見えにくい部分も含めて深く理解できているかどうかという観点は大切だと思います。
「E(Equity/公正)」については、アメリカでDEIのコーチングをしている友人の定義が私には腑に落ちています。教育の分野で言うならば、「誰もが同じ学びの場に立てるようにすること。そのために、必要な人に必要な支援をすること」。
つまり、学びのスタートラインに立つためには、子どもによって異なる支援が必要だという視点です。

かつては皆同じ道具を使うことが平等とされてきましたが、今は、教科書の文字が小さくて読みにくい子がいれば、タブレット端末で拡大表示して読む。この子は紙の教科書、この子はタブレット端末、それでいい。そうした配慮が、今でいう“合理的配慮”にもつながっています。
「I(Inclusion/包摂)」は、より感情や感覚に関わる話になります。自分がそのコミュニティの一員として「ここにいていい」「自分にも役割がある」「必要とされている」と実感できるかどうか。とても主観的な感覚ですが、だからこそ大切な要素だと感じています。
DEIを推進するとき、よく「ジェンダー格差をなくそう」「人種差別をなくそう」といったカテゴリーごとの議論がされます。それももちろん重要ですが、私は、あえてその“カテゴリー”にあまり触れず、“個人”としてのあり方に焦点を当てたいと思っているんです。
自分が社会の中にポンと置かれたときに、その環境をどう捉えるか。どうやって自分の力を発揮し、周囲とどんな関係性を築いていくか。公正さが100%保障される社会はすぐには実現しません。その中で「自分の足場を持ってしっかり生きていく力」を持つこと。そして「自分や周囲のウェルビーイングを高めていくスキル」を、子どもたちには小・中・高・大の教育の中で身につけてほしいと、私は願っているんです。
ーーDEIの視点を持つことは、先生たちにも必要なことだと思います。先生方へは、どのようにコミュニケーションし、根づかせていったのでしょうか?
例えば毎年、年度初めに出す学校経営方針では、私が大切にしている考え方を6つの重点目標として示しており、そのうちの2つ目の柱として「心理的安全性の高い組織文化づくりとDEIの推進」を掲げていました。
児童も教職員も、一人ひとりが安心して学び、働ける場をつくること。多様性の中で対話と協働を重ね、皆で成長していける学校にしていこうと、異文化感受性発達モデルも紹介しながら、概念をできるだけそのまま伝えるようにしてみたんです。
とはいえ、こうした言葉だけを並べても、先生方は「どうしたらいいの?」となりますよね。そこで、より具体的な行動指針として「お互いを支え合う意識を」「批判→提案」「対立→協力」という言葉を添えていました。
そうした具体的な行動に落とし込める言葉を受け止めて、実際に行動に移してくださった一部の先生方から、その影響が全体に広まっていったように思います。会議での発言の質が、より建設的な方向に変化しました。

もう一つ取り入れていたのが、平木典子先生の「アサーティブな自己表現」の理論です。
自分の意見や感情を正直に伝えること、それを相手がどう受け止めるかを見ること。これがアサーティブな自己表現の基本なのですが、平木先生はそこにさらに、「人間として誰もがやってよいこと」を自分にも相手にも認める、という考え方を加えているんです。
「人は誰もが自分らしくあってよい」「誰もが気持ちや考えを表現してよい」「間違えてもいいし、その責任を取ってよい」という3つの視点ーー特に、最後の「間違えてもいい」という考え方が、私はとても大切だと思っていて。
日本では、最初に言った意見を変えると「ブレた」と言われがちですが、私は話し合いの結果として意見が変わることは、むしろ建設的なことだと考えています。そういう姿勢を学校全体で共有できたら、どれだけ柔軟で強い組織になるかと。
他にも、「Equality(平等)」から「Equity(公正)」への考え方の転換についても触れながら、年に一度のこの機会を使って、理念と具体の両面から伝えようとしました。
ーー多様性の中で対話と協働を重ねることは、DEIを推進する上でとても大切なことですが、すぐにできるものではないと感じています。
おっしゃる通り、対話って「さあやりましょう」と言ってすぐにできるものではないですよね。対話や協働には、「自分には見えていないことがある」と認められる感受性が大切です。
違いや違和感を前にしたとき、「何か背景があるのかもしれない」「自分に見えていないことがあるのかもしれない」と想像する力。それが異文化感受性の出発点であり、DEIの根幹にもつながる大切な視点だと思っています。「自分には見えていないことがある」という前提に立てば、そこに謙虚に関わろうという姿勢が自然と生まれます。
例えば、大学教員出身で、小学校現場の経験も免許もなかった私にとって、小学校はまさに“異文化”でした。だからこそ「どういう風に教えているんだろう?」と純粋に興味があって、時間を見つけては教室を覗かせてもらっていました。
ただ、このときに気を付けていたのは、「校長=評価する人」という印象をなるべく持たれないようにすること。どんなに評価するために来ているわけじゃないと伝えても、やはり先生たちは構えてしまいますよね。どうしても校長という立場上、自分は意識しなくても、相手が感じるものはある。だからこそ、自分の立場が与える影響を自覚した上で、その圧をできるだけ減らすことも対話の土台づくりだと思っています。
勇気を出して、“見えない部分”にアクセスしよう
ーー「自分には見えていないことがある」という前提に立つ力を育むには、どうしたらいいのでしょうか?
大人の場合はまず、「自分には見えていないことがある」「知らないことがある」という意識をしっかり持っておくことが大切です。社会も子どもたちも日々どんどん変化していく中で、自分自身の認識や理解をいかにアップデートしていけるか。その意識は大前提として必要だと思っています。
とはいえ、「見えていないもの」が誰にでも簡単に見えるようになるわけではありません。そこにはやはり、知識や経験の積み重ねも必要です。知識の面では、理論や本に触れること。他者の視点を学ぶことは、自分のものの見方を増やす“レンズ”を与えてくれます。
そして経験の面では、自分の「当たり前」が通用しない場所に身を置き、そこで見えるもの、見えないものに意識を向けていくこと。これは本当に学びの宝庫です。
ーー子どもの場合はどうですか?
子どもの場合は、例えば、立命館小学校の海外研修の事前学習として、私が話をする機会がありました。その際によく「氷山モデル」を使って話をします。
異文化には“見える文化”と“見えない文化”があって、旅行なら見える文化を楽しむだけでもいいけれど、学びに行くときは、その下にある価値観や考え方といった“見えない部分”にこそ目を向けていくことが大切だよ、と。
その“見えない部分”にアクセスするきっかけは、「ちょっとおかしいな」「なんか違和感あるな」と感じたとき。そういうときこそ入り口だよ、と。そう言うと、子どもたちは「じゃあ掘ってみようかな」と、ちゃんと見えないところに意識を向けてくれます。
新しいことを学ぶときは、自分の価値観を揺さぶられたり、信じてきたことを問い直されて、傷つくこともありますよね。ただ、それこそが学びが起こる瞬間だと思うんです。
そういう“ちょっとした傷つき経験”をうまく成長に結びつけられるような力を育むためには、大人も子どもも、「知識を貪欲に学ぶこと」「自分の当たり前が通じない場所で経験を積むこと」「見えないものに想像力を向けること」の3つをセットで心掛けていくことが大切だと考えています。
持続可能なDEIの鍵は、先生一人ひとりのまなざしにある
ーー公立小学校では、人事異動などによってDEIの取り組みが継続しにくいという課題も聞かれます。持続的に推進していくためには、何が大切でしょうか?
制度や教材を整えることと同じくらい、先生一人ひとりの“あり方”が、DEI教育を持続可能にする鍵だと私は思っています。というのも、DEIに関する理念や知識は、すでに教科書や日々の授業の中にも反映されています。けれども、私が一番影響が大きいと感じているのは、先生の発言やふるまいなどに表れる、先生自身の“まなざし”です。
例えば「あの子は問題児だから」「困った子だから」といった言い方をされることがありますが、問題児と言われるときの起点は、子どもではなく大人側にあって、“大人都合”のラベリングになってしまっているんですよね。「この子がいるとやりづらい」「クラス運営が難しくなる」という状況を、その子自身のせいにしてしまっていないか。それは本当は自分(大人)の力量の問題ではないのか。教育者として、まずそこを問い続けることが必要だと思っています。
多様性の大切さを頭で理解していても、目の前の子どもに接するときに、その子の背景や違いにどれだけ感受性をもって向き合えているかは、先生の何気ないひと言や振る舞いに全てにじみ出ます。特に学校を引っ張る立場にある校長や教頭などが、「人は多様である」ということを深く理解し、自分の言動でそれを体現しているかどうかが、学校全体の空気にも大きく影響します。
もちろん、人間誰しも偏見や決めつけをしてしまうことはある。私自身にも「あ、私いまジェンダーバイアス持ってたな」とか「子どもに対して勝手に決めつけてたな」と気づく瞬間はたくさんあります。
でも大事なのは、そこに気づいて自分の思考や表現を修正していけるかどうか。「完璧な先生」ではなく、「自分の言動に気づき、考え、修正していける先生」であること。その姿こそ、DEIの価値観を子どもたちに伝える最も強いメッセージだと思っています。
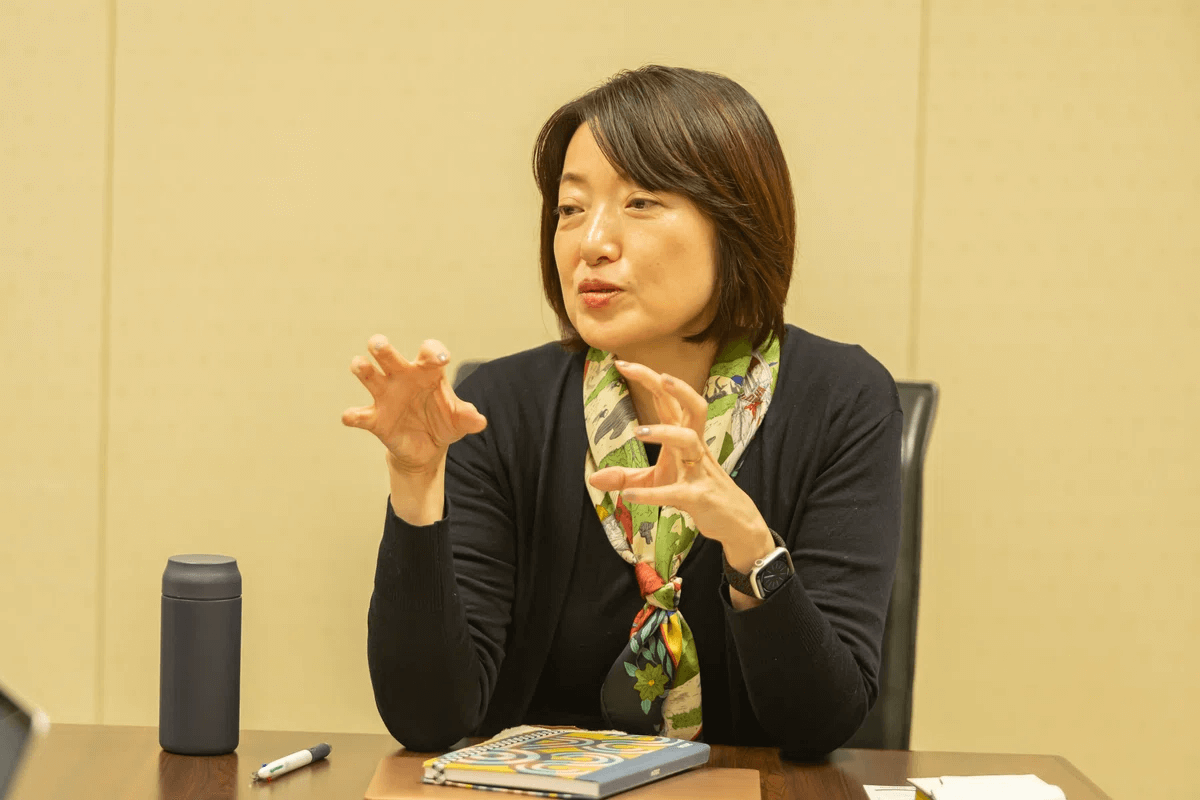
ーー子どもの頃から異なる価値観に出会い、向き合っていく経験を積むことが本当に大切なのだと感じました。
そうですね。いろいろな価値観や文化に触れるということは、その都度、自分の伝え方を細やかに調整したり、考え方に幅を持たせたり、価値観の違いを意識したりしているということ。そうした経験や“小さな努力”の積み重ねが、異文化感受性を高めていくのだと思うんです。
だからこそ、そうした経験を経た人は、他の人には見えない部分が見えるようになる。一方で、単一の文化の中で過ごしていては、そうした機微を読み取る力が育ちにくいという現実もあります。だからこそ、子どものうちから“自分とは違う価値観”に触れる経験を重ねておくことが、とても大切なんですよね。
学校は、それを安心して練習できる貴重な場所です。仕組みを整えれば、小・中・高・大という教育の中で、異文化感受性を育む機会を長期的な視野と効果的な工夫を持ってデザインすることができる。私は、学校こそがそうした力を育てるのに最適な場所だと考えています。
<取材・文・写真/先生の学校編集部>