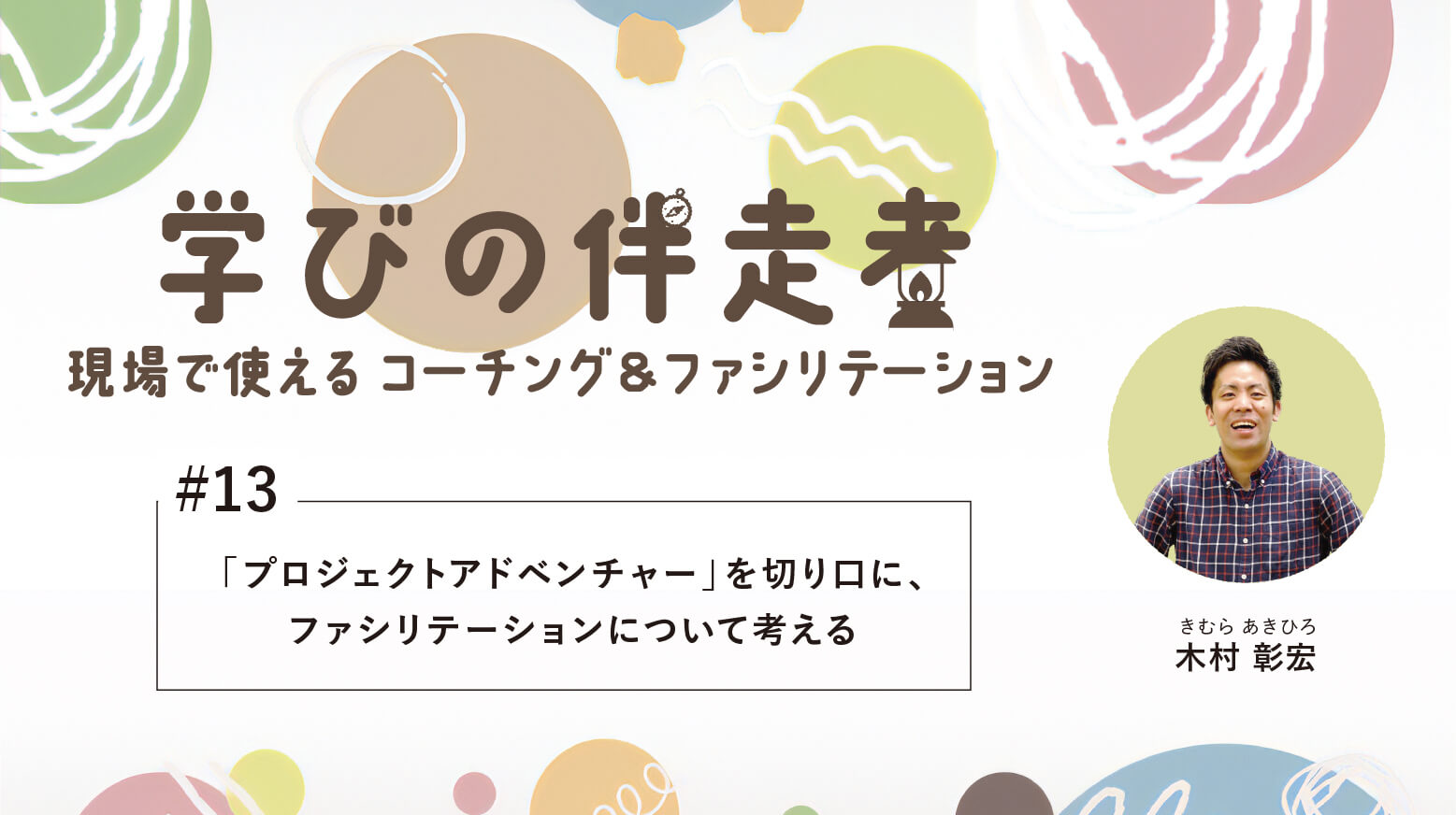6年間の探究×デザイン思考が、生徒の主体性に火をつける!ゴールは、探究学習を通じた自己実現

2014年に開校した鳥取県鳥取市にある青翔開智中学校・高等学校は、「探究・共成・飛躍」という建学の精神のもと、1学年約40人という小規模校ながら、2018年より文部科学省のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)に指定され、「デザイン思考」を取り入れた6年間にわたる探究プログラムを確立している。
年に一度、探究学習の成果を全学年で公開する「青開学会」には、毎年400人を超える来場者が集まるという。
そんな全国から注目を集める青翔開智中学校・高等学校で探究主任を務め、現在全学年の探究学習の指導に携わっている田村幹樹さんに、探究学習の詳しいカリキュラムや、探究を通じて見えた生徒たちの成長、探究主任として大切にされていることなどについて話を聞いた。
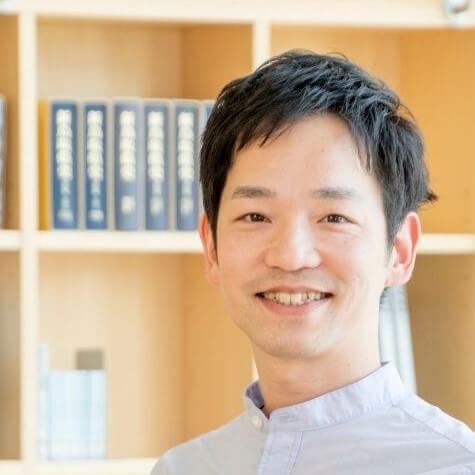
2006年より私立中高一貫校に勤務し、国の事業を活用した高大連携のあり方について模索。高大連携の取り組みについて学会発表(日本理科教育学会全国大会)を行い、山陰で初となる私立学校のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)校の立ち上げにも従事した。2016年より青翔開智中学校・高等学校に勤務し、山陰で2例目となる私立学校のSSH校立ち上げに従事。2020年より現職。
ゴールは、探究学習を通じた自己実現
——貴校は6年一貫の探究プログラムを確立されていますが、どのような教育計画で取り組まれていますか?
中学1年生から高校3年生まで、週に2時間(高1は週に3時間)、「探究基礎」という授業を実施しています。
探究基礎の集大成は、高校2・3年生で行う「自分の進路実現をどうするか」という課題研究です。
ゴールはあくまで「探究学習を通じた、生徒自身の自己実現」であると考えており、そのために必要なスキルやマインドを、探究基礎の授業をベースに教科横断的に育成しています。
具体的には、中学1年生では「アイデア創出」に主眼を置き、テーマに沿って共感を得られるようなアイデアをチームで創出していきます。

そして2年生ではビジネスの現場で活用されている思考法「デザイン思考」のフレームワークを使って、実際に課題解決に挑みます。
多くの中学校で職場体験を実施していると思いますが、本校では鳥取市内の地元企業を訪問し、「職業体験」をするだけでなく、「デザイン思考」を使って企業の課題を見出し、その解決プランを社長に提案します。
——社長に実際にプレゼンテーションをするんですね!
そうなんです。実際に、生徒が考案した商品アイデアを元に、地元特産品メーカーが商品化に着手したこともありました。
そして中学3年生では、「なぜそもそも課題を見つけて解決する取り組みが必要なのか」を深く思考していくマインドの醸成に主眼を置いたカリキュラムにしています。SDGsを切り口に、私たちの身近な課題を解決することが世界の課題解決につながっていることを体感してもらいます。
このように、中学校3年間を通して、新しいことを作り出す楽しさであったり、なぜそれをやらなければならないのか、というマインドを育みます。

——高校からはどのように展開されていくのでしょうか?
高校では、課題解決のクオリティを高めていくために、AIやブロックチェーン等のテクノロジーを活用していきます。
高校1年生ではAIやブロックチェーン等の技術をインプットし、それらを駆使して日本、そして鳥取の人口減少問題の解決に挑みます。
高校1年生まではグループワークで課題解決に取り組みますが、2年生からは、これまで身につけたデザイン思考や情報活用のスキルをベースに、1人1テーマで探究を深めていきます。
そのときに自分の(1)好きなこと、(2)得意なこと、(3)価値観、(4)社会が求めること、という4つの要素が重なる部分でテーマを設定することにしています。
自分がこの先どんなことをやっていきたいのか、進路選択を見据えて1年かけて取り組んでいきます。3年生では、2年生で取り組んだことを1万字の論文にまとめていきます。

——スキルやスタンスを時間をかけて醸成するからこそ、グループ活動から個人活動もスムーズに進むのでしょうか?
自分を確立している生徒はどんどん進んでいきますが、「自分は何者なのだろう?」という壁にぶつかり、スキルがあってもうまく進めない生徒も一定数います。
しかし、結果的には高校3年次に提出する論文の内容と進学先の方向性がある程度マッチしているので、悩むという過程が大事なのだろう思います。
ゴールは探究活動を通じた生徒自身の自己実現なので、その軸がブレることのないように、探究学習を推進しています。
教科の枠を超えて、全教員で探究学習に取り組む
——貴校では探究基礎だけでなく、教科横断的に探究のスキル育成に努めていらっしゃいますが、具体的にはどのように取り組まれているのでしょうか?
おそらく多くの学校では、探究をする上で必要となるスキルを、週に2時間の「総合的な探究の時間」の中だけで育成しようとしていますよね。
しかし、スキルの育成に比重を置くと本当にやりたい探究活動に時間を充てられなくなったり、逆に探究活動の時間を多く取ればスキルが身につかなかったりと、限られた時間の中でスキルの育成と探究活動を両立させるのは限界があります。
そこで本校では、各教科の授業の中でスキルを育成しています。

——探究をする上で必要となるスキルとは、具体的にはどのようなスキルでしょうか?
本校の「探究・共成・飛躍」という建学の精神を具現化するためのスキルを言語化することから始めました。
話し合いを進める中で、下記6つの資質を探究活動を支える「探究スキル」と総称し、各教科での取り組みを通して、体系的に育成することにしました。
1)課題設定
2)情報リテラシー
3)クリティカルシンキング
4)ロジカルシンキング
5)データサイエンス
6)表現
各教科でどのスキルが育成できるかをマッピングし、それらを集めて学校全体で「このスキルを育成する取り組みはたくさんあるけど、このスキルを育成する取り組みが足りていない」など、可視化できる仕組みを取り入れています。

——評価はどのように行っているのでしょうか?
探究においては、ルーブリック(学習到達状況を評価するための評価基準)を活用しています。探究の各段階でルーブリックを活用し、自己評価と担当教員による他者評価を行っています。
Googleフォームやスプレッドシートを活用して結果を共有することで、教員と生徒は研究の進捗をリアルタイムに確認することができます。集計の負担を減らすために、作成したルーブリックのデータを流し込むと自動的に結果が集約されるシートが作られるシステムも構築しました。
システムを教員だけで作るのは限界があるので、一般社団法人情報サービス産業協会(JISA)に加盟している企業のエンジニアの方々に協力していただいています。
——6年一貫の積み上げで生徒の主体的な学びを作っていらっしゃいますが、生徒の成長はどのようなときに感じますか?
これからの社会で使えるフレームということで取り入れたデザイン思考ですが、授業以外の場面でも、小さなグループでディスカッションする際に、ホワイトボードを使ってデザイン思考のフレームで話し合いを進める姿を見たときに成長を感じました。
自分が中高生の頃にはそういったツールを駆使しながら話し合いを深めることはできていなかったので、日常的に使ってきたからこそ見られた光景だと思います。
また、外部のコンテストに生徒が主体的に応募することが増えましたね。「この企画に応募して最終選考まで残りました!」など、知らないうちに自らコンテストに参加する生徒が出てきたことは、私がこの学校に来たばかりの頃との大きな違いですね。
これは探究学習だけでなく、教員が学校の外の世界とつながることの大切さを話したり、その姿勢を見せたりしてきたことによって得られた結果だと感じています。

学校の外へ目を向けて、社会の流れをつかむ
——探究学習を推進される上で、田村先生が探究主任として大切にしてこられたことは何でしょうか?
教育現場以外の、外の世界を見ることです。
例えばデザイン思考も、今は新しい思考法として注目されていますが、10年後には通用しなくなっているかもしれません。社会の流れと教育現場が乖離せず、常に時代が求めるものを追いながら、本質的なものを外さないために、外の世界を知ることを大切にしています。
企業の方と連携した取り組みの中でいろいろなことをディスカッションできることは、私にとって非常に有益な時間になっていますね。
また、これからの教育業界で求められていることを知るために、文部科学省のホームページはいつもチェックしています。例えば、中央教育審議会ではどのようなことがテーマに挙がっているのか、議論されているのか、これから何を求めようとしているのかなどを細かく見ています。
本校で取り組んでいることが先進的な事例として共感を得られることは、私学として非常に大切なことなんです。
——社会に開かれた教育課程を実現するために、自ら外の世界を見ることを大切にされているんですね。
そうですね。これから探究学習に本格的に取り組まれる学校も多いと思うのですが、先行して進めてきた学校としてアドバイスするのであれば、やはり「外の力を借りる」ことです。
例えば、地元の企業や大学とつながること、授業作りに関していえば他校とつながることが大切だと思います。閉じられた環境を打破しなければ、新しい「モノ・コト・ヒト」には出会えないからです。
外の力を借りることは、生徒にとっても、教員にとっても学びが大きいと思います。

——最後に、これから探究学習に取り組もうとされている先生方へメッセージをお願いします。
「探究」は新学習指導要領にも多用されて注目を集めていますが、真新しいことではなく、主体的な学びを実現するための方法論です。
アクティブラーニングやSTEAM等も同じで、流行りの言葉として受け取られがちですが、目指すべきところはどれも同じだと思っています。
教育の本質をいつも忘れず、未来の人材育成に最適な手法を常に模索し実践することが何よりも大切です。そして新しい教育の最適解にチャレンジすることをぜひ楽しんでもらいたいと思います。
〈取材・文=先生の学校編集部/写真=青翔開智中学校・高等学校提供〉